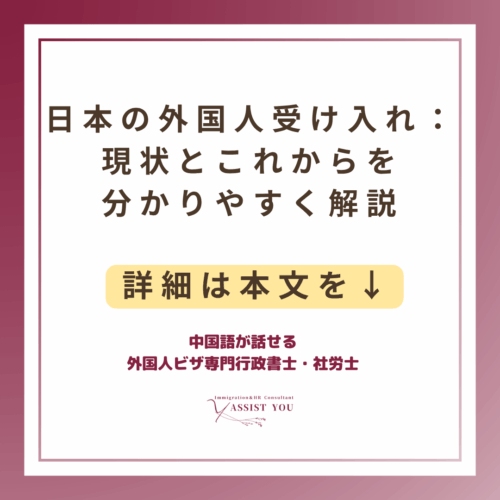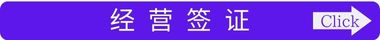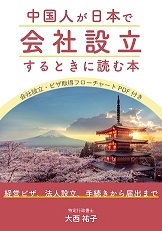ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
目次
なぜ今、外国人受け入れが大きなテーマなのか?
現在、日本の総人口に占める外国人の比率は約2.82% 10%台に達すると予測しています。人口減少が加速する日本にとって、外国人材は社会を支える上でますます重要な存在になっています。
だからこそ、「どのような外国人を、どのように受け入れるのか」というテーマが、今、私たち全員にとって非常に重要な意味を持つのです。
この文書は、複雑に絡み合う外国人受け入れ問題を、「経済」「地域社会」「治安」といった具体的な視点から整理し、初めてこのテーマに触れる方でも全体像を掴めるように手助けすることを目的としています。
1.基本的な考え方:日本の外国人受け入れ政策の「今」
まず、日本の外国人受け入れに関する基本的な方針と、なぜ今その見直しが求められているのかを確認しましょう。
1.1 伝統的な「二分論」という考え方
日本の外国人受け入れ政策は、伝統的に「二分論」という考え方を採用してきました。これは、受け入れる外国人を2つのカテゴリーに分けて、それぞれ異なる方針で対応するというものです。
- 専門的・技術的分野: 高度な知識を持つ研究者や技術者などを対象に、積極的な受け入れを推進する。
- それ以外の分野: いわゆる単純労働と見なされる分野を念頭に、国民的なコンセンサス(社会全体の合意)を踏まえつつ慎重に検討する。
この方針が、長らく日本の外国人政策の根幹をなしてきました。
1.2 なぜ今、政策転換が必要なのか?
これまで本格的な議論が避けられてきたこの基本方針ですが、今、大きな見直しの必要性に迫られています。その背景には、避けては通れない2つのキーワードがあります。
- 将来的な人口減少
- 経済社会の維持
人口が減り続ける中で、現在の経済や社会の仕組みを維持するためには、外国人材の力が必要不可欠であるという認識が広まっています。言い換えれば、これまで外国人材の受け入れについて戦略的な検討が十分に行われてこなかった(ソース1参照)という反省があり、場当たり的ではない、長期的視点に立った制度設計が急務となっているのです。
では、具体的にどのような視点からこの複雑な問題を考えるべきなのでしょうか。政府が整理している6つの重要な論点を見ていきましょう。
2.問題を整理する6つの視点
政府は、外国人受け入れ問題を多角的に検討するため、以下に挙げる6つの視点を提示しています。これらは、複雑な課題を解きほぐすための政府の分析フレームワークと理解することができます。
これらの視点は互いに独立しているわけではなく、時にトレードオフの関係にあります。例えば、「経済成長」を優先すれば「労働政策」や「地域社会」への配慮がより重要になる、といった具合です。このバランスをどう取るかが、政策の核心となります。
2.1 経済成長の視点
中心的な論点は、「継続的な経済成長のため、将来的にどの程度の外国人を受け入れることが適切か」という問いです。外国人材が日本の経済力維持・向上にどう貢献するのかを考える、マクロな視点です。
2.2 産業・労働政策の視点
この視点は、より具体的に産業と労働の現場に焦点を当てます。「どのような産業に、どのようなスキルを持つ外国人が、どの程度必要なのか」という産業政策の側面と、「外国人労働者が増えることで、日本人の雇用や労働条件にどのような影響があるか。また、外国人の適切な労働条件を確保できるか」という労働政策の側面の両方から考える必要があります。
2.3 税・社会保障の視点
外国人の受け入れが「税・社会保障制度にどのような影響を与えるか」も重要な論点です。外国人も日本に住む以上、税金や社会保険料を納める義務があります。近年、在留資格の更新や永住許可の審査において、納税や社会保険料の納付状況が以前よりも厳しく確認されるようになっています。これは、後のセクションで詳しく見るように、在留資格の更新ガイドライン(ソース6参照)で納税義務の履行が明記されたことにも表れています。
2.4 地域の生活者としての視点
外国人を単なる「労働力」としてではなく、私たちと同じ地域で暮らす「生活者」として捉え、いかにして真の共生社会を実現するかが問われます。言語の壁、文化の違い、子どもの教育など、地域社会が直面する課題を整理することが求められます。
2.5 治安の視点
政府は「国民の安全・安心を死守する」という強い姿勢を示しており、外国人受け入れが治安に与える影響は非常に重要な論点とされています。不法滞在者など、ルールを守らない外国人には厳正に対処する方針が明確に打ち出されています。
2.6 出入国及び在留管理の視点
現在の制度では、「特定技能」や「育成就労」といった一部の在留資格を除き、受け入れ人数の上限が設定されていません。今後、在留外国人の増加が確実に見込まれる中で、このままでよいのか、それとも「一定の受入れ上限数等を設定すべきか」という、量的マネジメントの是非が大きな議論となっています。
これらの視点は、外国人受け入れという大きなテーマを理解するための地図のようなものです。次に、この地図を使いながら、実際の制度がどのように変化しているのか、具体的な事例を見ていきましょう。
3.制度は変わる?具体的な在留資格の事例
複雑な制度を理解するために、特に課題が指摘され、見直しが進められている2つの在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「経営・管理」を例に、具体的な問題点と政府の対応策を解説します。
3.1 事例①:専門職のはずが…「技術・人文知識・国際業務」の課題
この在留資格は、大学卒業程度の専門知識を持つ外国人が、エンジニアや通訳、企画などの専門職に就くためのものです。しかし、本来は許可されていない単純作業に派遣労働で従事させられるといったトラブルが相次いでいます。
具体的な許可・不許可の事例
どのようなケースが認められ、どのようなケースが認められないのか、具体例で見てみましょう。
- 許可される例
- キャリアプランが明確な研修: 日本人の大卒者と同様に総合職で採用され、将来の幹部候補としてのキャリアプランの一環で店舗研修を行うケース(ソース7, 2-1-(7))。
- 専門性と報酬の整合性: 自動車工学を専攻した者が、日本人と同等以上の報酬で、専門知識を活かすサービスエンジニアとして採用されるケース(ソース7, 1-1-(13))。
- 不許可となる例
- 報酬が不当に低いケース: 同じ業務に就く日本人の新卒者よりも報酬が著しく低い場合(例:日本人18万円に対し、外国人13.5万円)。
- 在留状況が不良なケース: 留学生時代に、許可されたアルバイトの時間(週28時間)を大幅に超えて働いていたことが判明した場合。
3.2 事例②:起業家ビザの悪用防止へ「経営・管理」の厳格化
日本で会社を設立し、経営者として活動するための在留資格「経営・管理」ですが、本来の目的以外で悪用されるケースがあったため、政府は要件を大幅に厳格化する方針です。
変更点の比較表
項目 現行要件 見直し後
資本金・出資総額 500万円以上 3,000万円以上
経歴・学歴 なし 経営・管理経験3年以上 又は 関連分野の修士号以上
雇用義務 なし
(2人以上の雇用で資本金要件の代替が可能) 1人以上の常勤職員の雇用を義務化
事業計画の確認 なし 中小企業診断士等による事業計画の確認を義務付け
日本語能力 (規定なし) 申請者または常勤職員にCEFR B2相当を求める
※CEFR B2は、専門分野の技術的な議論も含め、複雑な内容を理解し、母語話者と自然にやり取りできるレベルを指します。
この見直し案に対しては、パブリックコメント(意見公募)で「更に厳格化すべきだ」という意見と、「これでは厳しすぎて小規模な起業家が挑戦できない」という両方の意見が寄せられており、社会的な関心の高さがうかがえます。
3.3 全体に共通するルールの強化
個別の在留資格だけでなく、日本に住むすべての外国人に対して共通して求められるルールも強化されています。在留期間を更新する際のガイドラインでは、特に以下の3点が重要な要素として考慮されます。
- 納税・社会保険料の義務 税金や社会保険料を適切に納めていることが求められます。特に、刑罰に至らなくとも「高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います」(ソース6)と明記されており、審査が厳格化されていることが分かります。
- 適正な活動 許可された在留資格の範囲内で活動していること。例えば、留学生がアルバイトの時間を守っているか、専門職の人が資格外の単純作業に従事していないか、などが問われます。
- 素行が不良でないこと 日本の法律を守り、善良であることが求められます。交通違反を繰り返したり、犯罪を犯したりした場合は、当然ながら在留にマイナスの影響を与えます。
このように、個別の在留資格だけでなく、日本に住む外国人全体のルールも強化されています。最後に、こうした方針を支えるための政府の具体的な取り組みを見てみましょう。
4.変化を支える体制づくり:政府の新たな取り組み
政府は、「国民の安全・安心」と「活力ある強い日本の実現」を両立させるため、システムの近代化と人員の増強という両面から体制強化を進めています。
4.1 水際対策と国内管理のデジタル化
厳格かつ円滑な管理を実現するため、デジタル技術の活用が進められています。
- 電子渡航認証制度(JESTA)の早期導入
- 目的: ビザが免除されている国・地域からの訪日客に対し、事前にオンラインで申請・審査を行う制度です。テロリストなどを水際で阻止し、厳格な入国審査を効率的に行うことを目指します。
- 在留カードとマイナンバーカードの一体化の検討
- 目的: 2つのカードを一体化することで、外国人の社会保険料の納付状況などをより正確に把握し、行政手続きの利便性を向上させることが検討されています。
4.2 審査・調査体制の人員増強要求
ルールを厳格に適用するためには、それを実行する「人」も必要です。法務省は令和8年度の定員要求として、大幅な人員増強を求めています。
- 令和8年度 増員要求数:1,103人
- 内訳(一部):
- 入国審査官:281人
- 公安調査官:101人
- 刑務官等:300人
これらの数字からは、審査や調査を強化し、ルールに基づいた適正な在留管理を徹底するという政府の強い意志が読み取れます。
5.まとめ:これからの日本の外国人受け入れ
これまで見てきたように、日本の外国人受け入れ政策は、大きな転換期を迎えています。
人口減少社会を支えるために外国人材の受け入れは必要不可欠である一方、それに伴う様々な課題に対応するため、政策は「より管理的で、ルールを重視する方向」へと大きく舵を切っています。
個別の在留資格の要件厳格化、納税義務の徹底、そしてそれを支えるデジタル化と人員増強。これらはすべて、無秩序な受け入れではなく、日本社会のルールの中で、貢献してくれる外国人をしっかりと受け入れていこうという姿勢の表れです。
「活力ある強い日本の実現」「国民の安全・安心の死守」。この2つの至上命題をいかにして両立させていくか。それが、これからの日本にとっての大きな挑戦であり、私たち一人ひとりが考えていくべきテーマなのです。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!